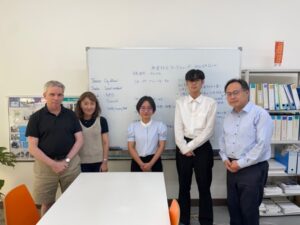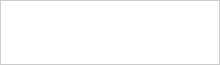この投稿の英語版はこちらからご覧いただけます。

今回、10日間のプログラムでインターンに参加していただいたベトナムの留学生のアインさんに海外のかたとの交流を目的に無電柱化を語る企画を考えていただきました。
彼女自身、高校・大学などでディスカッションをすることを経験されていることもあり、短期間ながらも的確で充実したミーティングを実施することができたので、簡単にその内容をご紹介させていただきます。
※彼女の作成したレポートは、英語版もあります。詳細は当NPOのHPで後日紹介させていただきたいと思います。
1. 基本情報
日時:2025年8月18日(月)14:00–16:00
場所:ジオリゾーム大阪オフィス 1F会議室
司会:Anh Van Bui
参加者:James Cusick、Junko Cusick、塚田泰二、間瀬天翔
2. スケジュール
14:00-14:15:アイスブレーカーと自己紹介
14:15-14:30:フリーディスカッション
14:30–15:15:ショートプレゼンテーションとQ&A
15:15-15:25:休憩時間
15:25-16:00:ロールプレイング
(1) ステークホルダーの役割説明(5分)
(2) ブレインストーミング(10分)
(3) 個人プレゼンテーション(20分)
16:00-16:10:ワークショップの振り返りとフィードバック
3. ワークショップの概要

Picture’ source: Google Image
ワークショップは自己紹介から始まり、参加者が電柱撤去への背景と関心を共有した。災害防止から街の美化まで、人々がこの問題の異なる側面を重視していることが明らかになった。
フリーディスカッションセッションでは、参加者が日本、ベトナム、アメリカでの電柱撤去活動を比較した。重要な歴史的事例として、キューシック氏より、1888年の大吹雪の後、雪と氷が電信線と電線を破壊したことを受けて、ニューヨーク市のすべての電柱が撤去された事例が紹介された。
ショートプレゼンテーションとQ&Aセッションでは、5カ国の目抜き通りの写真を使ったクイズゲームが行われた。参加者は、ベトナムのホーチミン市の「蜘蛛の巣」のような架空線に驚き、街灯、信号機、Wi-Fiアクセスポイントを統合したソウルの「スマートポール」システムに感動した。中には日本車が多く駐車している点から南アフリカ(正解はモザンビーク)と回答したケースもあった。ロンドンの写真では、オランダと回答するケースもあった。

Picture’ source: Google Image

Picture’ source: Google Image
続いて、電柱撤去の利点と課題についてのプレゼンテーションが行われた。
-
- 利点:災害対応力(台風、地震、嵐からの保護)、地域安全性(電磁波曝露の軽減)、景観改善(すっきりとしたスカイラインと開放的な眺望)
- 課題:経済面(高額な初期投資、維持費用、資金調達の負担)、技術面(複雑な設置工事、修理時間の長期化、地下空間の制限、工事の担い手不足)、地質面(岩盤地域や地下水位の高い地域での施工困難)
ロールプレイングセッションでは、参加者が異なるステークホルダーの役割を担った:
-
- 市役所職員(James):予算配分・資源配分・役割分担に焦点を当てた。競争原理が必要であるとともに、実行をサポートするNPOの役割が重要であるとした。
- 地域住民(Junko):安全性と美化を重視した。災害対策が重要であることはもちろんだが、無電柱化をもっとビジネスとして転嫁すべき。使わない電柱をセメント材料としたり、発展途上国に無電柱化技術を提供しては。あと電柱・電線がはびこっている場所=治安の悪い場所(ブロークン・ウインドウズ・エフェクト)・poor(貧しい)場所というイメージからの払拭。現在の日本で問題になっている空き家問題と同様に有効な政策が実行されず、おざなりになっている現状。優先順位をつけながら空き家問題と一緒に解決していく必要あり。
-
- NPO代表(Tsukada):コミュニティ参加を支援した。高圧線による森林火災のリスクはないのか。電磁波の影響はないのか。日本の被覆技術のよさを活かした浅層埋設での無電柱化ができないか。←高圧線の浅層埋設は難しい。リスクが高い。
-
- 観光客(Tsubasa):美観に対する来訪者の視点を共有した。オーバーツーリズム・リッチな旅行者には観光税を引き上げて予算の運用にあててはどうか。治安・安全面も重視したい。
-
- 電力会社職員(Anh):電柱・電線は、外部不経済(いわゆる公害)であることの認識の欠如、コスト、技術的問題、運用に関する懸念を提起した。
これらの視点を通じて、グループは電柱撤去が日常生活と災害対応力にとって重要である一方、財政的・技術的障壁が残っていることを認識した。参加者は、成功的な実施には政府、民間セクター、NPO/NGOの協力が必要であり、大規模な電柱撤去を可能にするための新しい資金調達手段を創造的に生み出す必要があると結論づけた。

4. 感 想
James Cusick:
アンさん、ワークショップを開催していただきありがとうございます。あなたは会議の進行に素晴らしい仕事をしたと思います。個人的には、意見を提供し、他の参加者から学ぶ機会が十分にあると感じました。
以下にリストアップするいくつかのアイデアがあります。
しかし、その前に、メモを取ることについて、ちょっとした提案をします。私の経験では、ファシリテーターは通常、セッションの指導に忙しすぎて、大量のメモを並行して取ることができません。多くの場合、人々はボランティアにメモを取ってもらうことを依頼します。通常、誰かが申し出ます。これにより、ファシリテーターはやるべきことがあり、ファシリテーターは会議の流れに集中できるようになります。もちろん、ファシリテーターもメモを取り、ボランティアのメモテイカーと組み合わせることができます。
さて、アンダーグラウンド化(電線類地中化・無電柱化、以下同じ)についての考えをいくつかご紹介します。
-
- 押して引く
NPOや他のアンダーグラウンド化の提唱者は、その取り組みを推進できると思います。ただし、コミュニティには、このアプローチを取り入れたいプレイヤーもいるはずです。これらのつながりを構築することは、成功に不可欠です。 - ショーケースツアー
おそらく、興奮を高める方法の一つは、(大阪で打ち合わせした)オフィスを訪れた際に見た梅北公園エリア(p.11のチラシの写真参照)のようなサクセスストーリーを人々に見せることです。架空電線が乱立する旧態依然な状態の地区と、きれいに整えられたエリアと比較して見ると、美的優位性が明らかになると思います。 - メディア戦略 ワークショップに参加したいが、その日は忙しかった知り合いがいます。彼はメディア問題に関して非常に経験豊富で、来週会い、NPOの地下活動を促進するための彼のアイデアについて話し合う予定です。この会議の結果についてアドバイスします。
アンダーグラウンド化を推進するにあたっては、例えば、日本を美しくする、安全性を高める、経済活動を拡大するなど、ほとんどの人が共感できるリードメッセージから始めるべきだと思います。このようなメッセージは、直接的で、かつ明確で、魅力的であり、同じ方法で頻繁に繰り返されるべきです。 - 魅了する 地下化を推進するにあたっては、例えば日本をより美しくする、安全性を向上させる、経済活動を拡大するといった、多くの人が共感できるリードメッセージから始めるべきだと思います。そうしたメッセージは、的確で明確、そして魅力的で、同じ形で何度も繰り返されるべきです。
- 一般的な議論を解除する コスト、優先順位、規模など、特定の共通のテーマに沿って人々がアンダーグラウンド化に抵抗していることに気づきました。これらの一般的な議論をいくつかリストアップし、前もって答えを提供しておくと、人々が地下化が機能しない理由について考える必要がなくなります。
- 明確な財務モードを提供する 地下化のコストを明確に記載する必要があります。たとえば、新築のキロメートルあたりのコスト、既存面積の転換のキロメートルあたりのコストなどです。また、これらの費用を賄うための潜在的な資金調達モデルは何かを考える。
- 災害復旧のメリットを定量化する 投資要件が明確である必要があるのと同じように、メリットも明確である必要があります。たとえば、理論的には、都市の架線施設が地下に埋設されているのを考えた場合、災害後の初期対応者の予想速度はどのくらいになるのか。あるいは、回収コストの削減などはどうなるのか。富士山の美しい写真スポットの観光客人気に数字を付けてもいいかもしれません。
- 押して引く
これらは考慮すべきアイデアのほんの一部です。
繰り返しになりますが、アインさんにお会いできてとてもうれしく、残りの研究と将来の学業の幸運を祈ります。
※Cusick氏の文章は英語でいただきましたが、グーグル翻訳などを使って日本語訳したものを掲載させていただきました。
Junko Cusick氏
“まずはアインさん、皆さまお疲れ様でした。アインさんにはワークショップの前に一度お会いしたことがあるのですが、会ってすぐ彼女の聡明さ、明るさに感動し、加えてとても国際性豊かなでオープンな方とお見受けしました。ワークショップではまさに私が感じた通り、それ以上の出来栄えで、とても楽しく参加させて頂きました。
私達の勝手な素人の意見にも関わらず、丁寧に進めて下さり、また堅苦しくなく自由に述べさせて頂けたのも、NPO無電柱ネットさんのカルチャーと塚田さんが機会を作って下さったおかげだと感謝しています。
ワークショップの企画、準備、日英両方の言語での説明、進行など、慣れていらっしゃるとは言え、大変だったと思います。彼女のような優秀な若者が日本にいて下さることはとても嬉しいことですし、これからもますます自由に情熱的に勉学その他に打ち込まれ、ご活躍されることをお祈りしています。
無電柱化は災害大国日本にとって、重要な課題にも関わらず、少しずつしか進まないのがはがゆいですが、国際的な視野からの話し合いもきっと役に立つと思います。カジュアルな会合でもまた皆さんとお会いでき、少しでも地中化が、ベストな方向へと繋がっていけばと祈願しています。この度はありがとうございました!“
塚田泰二:
インターンの指導者という立場も兼ねて参加させていただきました。
まず最初に、私たちの今回の企画に共感をいただき、色々な助言とお知り合いのご友人に声をかけていただき、無電柱化についてのご意見まで集めていただいたキューシックご夫妻に深く感謝申し上げます。
本題ですが、今回の運営・司会を担当されたアインさんに敬意を表したいです。ファシリテーターとしての役割を立派に務められ、深みのある、かつ楽しいミーティングになり、良い成果を得ることができました。インターンに費やす時間が80時間というスケジュールの中で、企画・交渉・運営・振り返りまでをしっかり進めていただきました。
本人にうかがうと、このようなディスカッションのは結構経験されているとのことで、日本の学生とは違う面を感じました。
今回のワークショップの具体的な評価に移ると、
-
-
- グループディスカッションという運営をしっかり身に着けて実行しているところ
- タイムスケジュールの時間配分や各セッションを行う意味が参加者に伝わる構成になっていた。
- 参加者が緊張することなく、かつ各自の意見を引き出せるような構成になっており、「これぞディスカッション」という時間を共有することができた。
- 特に4.のロールプレイングでは、参加者に様々な立場で無電柱化を考えさせるアイデアを設け、各自の発表後には、発表者以外が意見を補うという、活発な議論が事前に創造できるような構成にしていたところが印象に残りました。
-
今回のワークショップに参加いただいたキューシックご夫妻は、無電柱化に精通されていて、関心の深いかただったので、アインさんの企画に多大な後押しをしていただいた点もありましたが、お二人の意見をうまく引き出してよいミーティングになったのもアインさんの考えたこの構成と話しやすい雰囲気の演出があっての成果と考えています。
今回のワークショップの企画は、今後の日本の学生が運営する学生討論会にも使えそうですし、海外のかたと議論を深めるミーティングにも応用できる素晴らしい企画だと思います。私自身大変参考になり、勉強になりました。
アインさん、Good job:グッジョブでした。ありがとうございます!
間瀬天翔:
私にとって今回のワークショップは、無電柱化について日本のみならず世界にも視野を広げるきっかけとなりました。日本の電柱に溢れた景観を他の国の景観と写真を通して直接比較することは視覚的にも刺激になりました。ただ受動的に学ぶのではなく、クイズや別々の立場に立って無電柱化について討論する時間など、能動的に働きかける機会が数多く用意されていたため、楽しみながら知識を深めていくことができました。私自身、海外の方を直接招いてでの議論は初めてなので緊張しましたが、すごく良い経験になりました。
Cusickご夫妻は無電柱化について非常に詳しい方々で、無電柱化に関する知識だけではなく、世界中をまたにかけてお仕事され、旅して培った経験や、大学で教えておられる教授ならではの研究や専門知識から生まれる斬新なアイデアを沢山出していただきました。私には思いつかないような意見や事実、私とは異なる意見を伺えたことも非常に有意義でした。私もいつかそのような深い知識と経験をもって議論の場に臨めるようになりたいと思いました。
今回私をこのような場に参加させていただいたNPOの塚田さん、企画運営に司会まで務めてくださったアインさん、お忙しい中参加していただいたCusickご夫妻、本当にありがとうございました。
Anh Van Bui:
今回のワークショップでは、まず「なぜ」電柱を撤去する必要があるのかを理解することの重要性を学びました。目的を明確にすることで、社会的な説得力が高まり、より多くの支持を得ることができます。世界各国の事例研究の紹介も非常に有益であり、防災、安全性、都市景観といった観点から、各国がどのように課題に取り組み、どのような要因が決定を後押ししたのかを知ることができました。
また、先進国の経験が資金や技術力に限界のある途上国にも適用できるのかという点についても考えさせられました。さらに、創造的な資金調達の方法についての議論も印象的でした。例えば、日本政府による空き家や空き地の売却、高度な地中配線技術の輸出といったアイデアは、革新的な発想が新たな実行の機会を生み出せることを示しています。今回のワークショップは、電柱撤去における課題と可能性の双方をより深く理解する機会となりました。
また、ワークショップでは司会を担当し、進行や参加者対応で手一杯になり、十分にメモを取れず、内容をまとめる際に非常に困りました。今後は、ワークショップやミーティングでも自分でしっかりメモを取れるよう、事前に練習や工夫を重ね、効率的に記録できる力を身につけたいと思います。