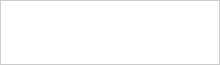なぜこんなに電柱が増えたのか?
手短に言えば、「早く・広く・安く」が勝ったからだ。
掘るより立てる、複雑な調整より占用許可、共同溝より単独工事。戦後から高度経済成長にかけての日本では、この選択肢が最も適していた。地中化は理念としては美しいが、実装としては鈍重であったのである。重要なのは、当時は暫定だった合理が制度や慣行によって固定化し、強い慣習になっていったことだ。考え直さなくて済むので便利であるが、その便利さは景観という資産をじわじわと削り、将来の選択肢を狭めていく。
無電柱化が進まない要因
最大の壁は費用である。
1kmで数億円という数字が出てくれば、それだけで議論を止めることになる。しかしよく考えてみると、初期費用にのみフォーカスが当てられ、更新費や事故、倒壊に伴う外部コスト、観光・居住の魅力としての景観価値の上昇などの視点が見落とされてしまっている場合が多い。
次に、関係者との日程が合わない問題がある。
電力、通信、道路、上下水道、沿道者…誰がいつ掘るのか、誰がどこまで負担するのか。さらに人によって復旧思想が違うのもある。
地震直後の目視点検や仮復旧は地上設備の方が早い一方、自然災害には地中が強い場面もあるのに、議論はいつも”どちらが絶対的に優れているか”のような極端な方向に傾き、最適化の話が真ん中に来ないのだ。
そして文化の問題もある。
日本では景観よりも書類上の数字のほうがはるかに強い効果を発揮する。
なぜなら景観を損ねても請求書は届かないからだ。結果として見える損失が常に優先される。
そもそもなぜ無電柱化が必要なのか?
必要性は景観だけの話にとどまらない。
まず防災と安全である。
電柱倒壊による道路閉塞を避け、感電や延焼のリスクを下げることは、外見の話ではなくて人の安全を守るために必要な対策だ。
次に、景観は投資でもある。写真と動画が観光の入り口になった時代、きれいな空と街並みを整えることは広告費削減に繋がる。都市機能の観点でも、歩道の幅が広がればベビーカーや車椅子が動きやすくなるし、自動運転の視界・センサーの安定にも直結する。副次効果として、照明やカメラ、環境センサーの配備がしやすくなり、夜間の安心感向上につながる。つまり無電柱化は、防災×機能×ブランドの複合的な投資なのである。
皆さんのご意見をお待ちしています。
私は今夏インターンに参加している学生です。
皆さんのご意見をお待ちしています。
最後にもう一つお願いします。
今夏のインターンでは、『大学生向け「無電柱化」知名度調査アンケート』を実施しています。
大学生の皆さんや、お知り合いで大学生の方がおられましたら、是非「無電柱化」の知名度調査にご協力をお願いいたします。
【2025年夏】大学生向け「無電柱化」知名度調査アンケートのお願い