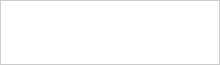ヨーロッパはなぜ進んでいるのか
ヨーロッパはなぜ無電柱化に関して進んでいるのだろうか?
それは戦後復興と歴史的景観保護が法制度で結びつき、道路や上下水、電力・通信を一気に更新する方法が採用されたからだ。
掘るなら一度に、まとめて整備することを意味する”Dig Once”はスローガンであると同時に実務手順を示す運用指針であり、これは設計時に地上より地中側にインセンティブを傾ける。
台北・ソウル・ジャカルタが無電柱化を進める理由とアジアの実利主義
台北では主に台風による被害が安全ロジックを鍛え、国際都市としてのブランド戦略が外見を後押しした。
ソウルは1988年のオリンピック後の都心再生を契機に政府が主導となって道路整備や上下水更新・電力/通信の地中化をまとめて一つの事業として進める同時化を標準化した。観光と景観を外貨獲得の窓口として位置付け、投資として扱っている。
ジャカルタは洪水対策と都市近代化を外資誘致パッケージに統合し、”見える線”である都市交通と”見えない線”である地中化を同じ設計図の上で進めている。
これら三都市に共通するのは、大型プロジェクトと抱き合わせで一気に実施する設計であり、問題を一つずつ点でつつくというより線で解決する方針である。
日本の進め方は今のままでいいのか
日本の状況を完結にいうと現状維持である。
全国一律で進めている無電柱化は、費用対効果が低く、地震や台風などの災害時の初動は地上設備に分があり、住民の無電柱化へのニーズも相対的に低いと考える。
筋は通っているが、評価が初期費用に偏っていることや、ハザード別の使い分けの不足、そして”後掘り”を前提にしたまま時間を浪費する設計が弱点である。
一方「もっと進める」立場は、防災・国際競争力・将来の都市機能のために必要だとするが、財源と優先順位の設計が情緒に寄りがちである。
ここで現実的な路線は、まず優先度を見える化し、観光回廊や都心幹線、避難・救急動線といったところから着手することだ。
新規開発は原則無電柱化として将来の当たり前を先に固定し、「Dig Once」を条例などで義務化、占用料と補助のインセンティブを地中側にもっていく。浅層埋設・共同溝は地図ごとに使い分け、財源は観光税や沿道の、企業版ふるさと納税の景観枠を組み合わせる。
成果はKPI―倒壊件数、復旧時間、通行量、事故率、観光消費、沿道地価―で年ごとに公開し、国民に向けてこれらの政策は臨機応変に対応であることを宣言する。これなら全部一度に無電柱化することができなくても、効果の大きい部分から着手でき、暮らしやすい生活に向けて一歩前進できる。
皆さんのご意見をお待ちしています。
私は今夏インターンに参加している学生です。
皆さんのご意見をお待ちしています。
最後にもう一つお願いします。
今夏のインターンでは、『大学生向け「無電柱化」知名度調査アンケート』を実施しています。
大学生の皆さんや、お知り合いで大学生の方がおられましたら、是非「無電柱化」の知名度調査にご協力をお願いいたします。