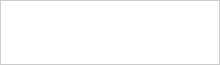1.はじめに
今回、私がお世話になっているインターン先は、NPO法人「電線のない街づくり支援ネットワーク」という団体です。私は神戸学院大学現代社会学部・社会防災学科に所属し、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた防災について学んでいますが、その学びを活かし、このNPOの活動に少しでも貢献できればと思い、今回インターンに参加しました。防災、特に地震における無電柱化の重要性について、インターン活動を通じて学んだ事柄を以下に記述します。
2.電柱がもたらす3つの災害リスク
日本は災害大国であり、電柱が存在することで以下のような危険が生じます。
・台風や竜巻による電線の切断・停電
→強い風によって電線が切れ※、家屋だけでなく、街灯や信号が消えるなど電線の被害は生活に大きな影響を与えます。
・豪雨による停電の発生
→大雨による土砂崩れや洪水で電柱が倒れたり、電線が切れることで大規模な停電が起き、暮らしや安全に大きな被害をもたらします。
・地震による電柱の倒壊
※電線の断線は主に電柱の倒壊によるものや飛来物との接触、街路樹の倒木などがあります。
3.地震の種類と無電柱化の必要性
地震は大きく「直下型地震」と「海溝型地震」の2種類に分けられます。
(1)直下型地震(例:阪神・淡路大震災)
震源が市街地の直下にあり、局地的に強い揺れを起こします。建物の倒壊や火災が発生することによって緊急車両の出動が必要となりますが、電柱が倒れて道路をふさいでしまうことがあります。電柱には感電の危険があるため、処理は電力会社でなければできません。無電柱化されていれば、こうした障害を避けることができ、一刻も早い人命救助につながると思います。
実際、阪神・淡路大震災では電力用電柱約4,500基、通信用電柱約3,600基が倒壊しました。
(2)海溝型地震(例:東日本大震災)
海溝付近で発生し、広範囲に被害を及ぼすのが特徴です。津波の被害が大きく、直下型と同様に電柱が障害となる可能性があります。
無電柱化の効果を考えると、特に直下型地震への備えとして重要だと感じました。
4.道路インフラの重要性
直下型・海溝型のいずれにおいても共通して言えるのは、災害時に人々が必ず利用する「道路インフラ」が極めて重要だということです。建物の耐震化や津波避難タワーと同様に、道路の安全性を確保することは、防災において最優先で取り組むべき課題だと考えます。
5.おわりに
今回のインターンを通して、日本は先進国でありながら、無電柱化が十分に進んでいない現状を強く実感しました。今後はより早い段階で、無電柱化が進むことを望みながらも、災害に強い街づくりの実現に向けて優先順位をつけながら国・自治体・電線管理者の皆さんが中心となって無電柱化を進めていくことを期待しています。(遠藤)