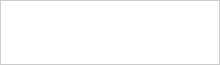皆さん、こんにちは!
私は今年の夏休みを利用してインターンに参加している森田です。
現在は、無電柱化の知識を学びながら、どうしたら無電柱化を知ってもらえるかの企画を考えています。
今回は、「無電柱化と防災」に関してサクッと解説していきたいとおもいます。
参考にした当NPOの記事電柱と災害との意外な関係。無電柱化のデメリットの実態とは!? | NPO法人 電線のない街づくり支援ネットワーク
1.無電柱化と防災
皆さんは以下の画像を見て何を感じますか?

この画像は、2018年9月4日に襲来した台風21号による電柱の倒壊の画像です。
災害時に電柱が倒れると、緊急車両の通行の妨げや停電などのインフラの障害、建物が下敷きになったりと、多くの被害が発生します。
2.電柱はどれほどの風に耐えられるのか
電柱は風速何m/sに耐えられるよう造られているかご存じですか?
「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第2章第3節32条には
「架空線路または架空電車線路の支持物の造りは、その支持物が支持する電線等による引張荷重、風速40m毎秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化、振動、衝撃その他の外部環境の影響を考慮し、倒壊の恐れがないよう、安全なものでなければならない。」とあります。
つまり、電柱を立てるには40m/sに耐えられる素材と造りでなければならないのです。
ここで、日本の歴代風速ランキングを見ていきましょう↓↓

40m/sをゆうにこえていますね…はたして今立っている電柱は安全なものといえるでしょうか?
3.日本は地震大国
2016年4月14日に発生した熊本地震では244本の電柱が倒壊し、477万戸の世帯に停電などの影響が出ました。しかしながら九州電力は、地中線への影響はなかったと発表しています。
みなさんは電柱の耐震基準をご存じですか?
先ほど述べた「電気設備に関する技術基準を定める省令」の第2章第3節32条には、風速に関する規定はあっても耐震に関する規定は定められていません。かつて震度7を記録した阪神淡路大震災では、すべての電柱が倒壊したわけではありません。 しかしながら、震度7ともなれば電柱が倒壊し、停電や道路の寸断などが起こっています。また、1回目は倒れなかったとしても2回目はどうなるかわかりません。すなわち、耐震基準がないからと言って電柱を放置していい理由にはならないのです。
しかしながら、震度7ともなれば電柱が倒壊し、停電や道路の寸断などが起こっています。また、1回目は倒れなかったとしても2回目はどうなるかわかりません。すなわち、耐震基準がないからと言って電柱を放置していい理由にはならないのです。
4.そこから言えること
そもそもなぜ日本に電柱が林立しているのか。それは、戦後の経済復興を優先し安定した電力供給を早急に整備するためです。また、裸線ではなくコーティングされた電線のため地中化の必要がありませんでした。しかし、その電柱や電線で我々の生活が脅かされています。地中化されている電線は災害時に被害を拡大させることもなくインフラ機能も継続することができます。
災害の被害抑制や救助の増進、災害時のインフラ機能継続のために無電柱化を積極的に進めてみませんか?
最後までご覧いただきありがとうございました!
ボランティア・インターン生募集 | NPO法人 電線のない街づくり支援ネットワーク